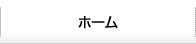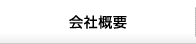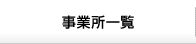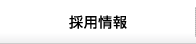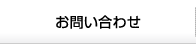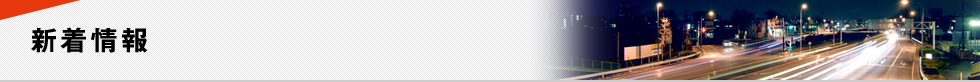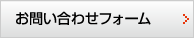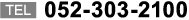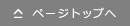大規模イベントが運送業に与える影響

大阪・関西万博2025が、半年間の会期を経て10/13に閉幕しました。
万博終了を経た今、「大規模イベントが運送業界に与えた影響」を考察してみたいと思います。
まずは、会期前後に展示物や建設資材、設備、補修部材などの搬入・設営輸送が集中しました。また、飲食・物販などの資材配送も並行して走り、物流拠点やトラック稼働率には強い負荷がかかりました。輸送スケジュールやルートの制約も多く、業界各社はピーク時対応の体制を組む必要があったと考えられます。
会期中は、来訪者輸送優先のために道路使用規制や交差点制御、専用レーン設定などが実施され、これが物流車両のルート選定や配送時間帯に大きな制約を与えました。
万博が終わると、運搬・設営物資の撤去・回収も発生しますが、通常取引の輸送量は一時的に落ち込みやすくなります。
特需に対応するために拡張した車両数・拠点体制・人員が、万博終了後には遊休化するリスクもあります。つまり、「過剰なキャパシティ拡張」 →「終了後の需給ギャップ」をどのように乗り切るかが課題となります。スケーラブルな車両・人員体制、多用途運用可能な設備設計が求められます。
夢洲駅は、大阪メトロ中央線の延伸区間として開業しましたが、閉幕後に利用頻度も落ちることが予想され、運用本数が縮小されることもあります。
イベント期で確立されたアクセス構造が、閉幕後もそのまま継続されることは考えにくく、縮小・変更が考えられます。その場合、それに合わせた物流ルートの変更も必要になります。交通規制や混雑必至の時間帯に依存しない、夜間配送・深夜配送や交通負荷軽減ルートの常時確立も、イベント対応力を高める鍵になると思います。
また、大阪・関西万博は「未来社会のデザイン」がテーマであり、持続可能で先進的な技術導入の舞台ともされました。
今後の運送業界にも以下のような実験・取り組みが想定・実行される可能性があります。
・EVトラック・燃料電池車など環境対応車両の導入促進
・共同配送・集約配送システムの拡充
・IoT・リアルタイム物流情報共有プラットフォームの運用
・自動運転や無人搬送システム、一部ドローン物流実証
これらは「万博対応」という枠を超えて、今後の通常物流モデルにも大きく影響を与えることでしょう。